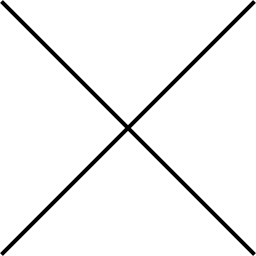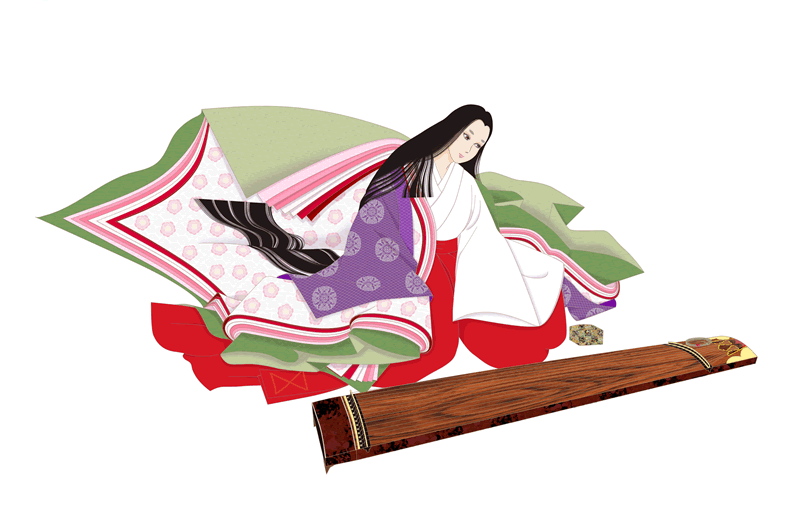
和歌 在原業平について
六歌仙、三十六歌仙の一人。
後の世の紀貫之に「その心あまりて、言葉足らず」と言わしめたほどの和歌の才を称えられています。
在原業平作と言われる伊勢物語の、「月やあらぬ 春や昔の春ならぬ わが身ひとつは もとの身にして」の歌について、ネット上でこんな解説があります。
意味については、次のように訳してあります。
月はちがう月なのか。春は過ぎた年の春ではないのか。私だけが昔のままであって、私以外のものはすっかり変わってしまったのだろうか。
そして、鑑賞として以下の様に続きます。
昔、東の京の五条通に面した邸に皇太后がおいでになった。その邸の西の対の屋に住む女がいた。
男は、その女と望ましくないとわかってはいたが逢瀬を重ねていた。正月の十日くらいに、女は五条の邸からいなくなったが、いる所は人に聞いて分かった。
しかし普通の身分では往き来することができる場所ではないので、男は思いを募らせつらいと思った。
男は、翌年の梅の花盛りの折に、女の住んでいた屋に行ってはみたが、女と過ごした時が過去のものだと思い知り泣く。
男は夜中すぎまで屋で横たわり、去年を思い出して歌を詠んだ。
逢瀬の重ねた夜と同じように、月も照り梅も薫り早春の夜の趣で、自分の恋情もまた昔日と同じであるのに、相手の女性がいないというたった一つの違いがもの寂しくやるせなく思わせ、涙している。
この相手の女性は清和帝の女御となる二条后で、西の対の屋から姿を消したのは後宮に入ったためである。
解説を見て頂いてわかる様に、表す内容に対して、世の中の言葉が、足りなすぎるといわれるのも頷けます。
また、和歌の世界では、修辞法と呼ばれる表現技法があります。これだけ書いても分かりにくいと思いますが、簡単に説明すると和歌専用の修辞技法だと思ってください。
主な修辞法だけでも、枕詞、掛詞、序詞、縁語、句切れ、体言止め、折句(冠)(沓)(沓冠)、物名、係り結び、対句、本歌取り、などがあります。
在原業平の有名な歌を例に解説を含めて引用しますので参考にしてください。
先程の一首と同じく伊勢物語より東下りの有名な一句です。
「から衣、きつつなれにし、つましあれば、はるばる来ぬる、旅をしぞ思ふ」
歌の意味は次のようになります。
着つづけて体になじんだ唐衣のように、なれ親しんだ妻が都にいるので、都を遠く離れてはるばる来てしまった旅をしみじみと思うことだ。
この「から衣…」の歌に使われている修辞は以下の5つです。
①枕詞(まくらことば)
②序詞(じょことば)
③掛詞(かけことば)
④縁語(えんご)
⑤折句 【冠】(おりく)
まず枕詞。これは特定の単語、熟語を装飾する言葉です。
この場合は、「から衣」が枕詞となり「きつつ」にかかります。
続いて、「から衣 きつつ」の部分が序詞となり、その直後にある「なれ」にかかってきます。見てわかる様に枕詞と序詞はよく似ていて分かりにくいですが、長年のうちに決まりごとになっているのが、枕詞で自由度を持って使えるのが序詞です。
そして掛詞、同音異義語を使って、1つの言葉に2つの意味を持たせる「ダジャレ」のようなものです。31音しかないこの歌の中に、なんと4つの掛詞が使われています。
なれ:「馴れ(慣れる)」と「委れ(着物が着古されることで、くたびれること)」
つま:「妻(奥さん)」と「褄(着物の袖)」
はるばる:「遥遥(距離が遠いこと)」と「張張(着物が糊付けされてぴんとしていること)」
き:「来(来る)」と「着(着る)」
次は縁語です。
これは、特定の言葉をに対して、関係の深い言葉を使っていく表現技法です。
「衣」に対し縁の深い「き(着)」「なれ(委れ)」「つま(褄)」「はるばる(張張)」の4つの単語が使われています。
最後に折句です。
からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ
この歌を仮名にし、頭を青色に変えています。
この青色部分を拾って読むと『かきつはた』が浮かんできます。
今でいう『縦読み』がこれにあたります。
このように、様々な修辞法を一首の中に盛り込むことによって、歌の内容以上に奥深い洒落の効いた遊び方をすることが可能になるのです。
次回からは、代表的な修辞法について一つ一つ、実例を挙げながら説明していきたいと思いますので、楽しみにしてください。