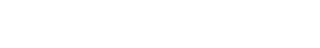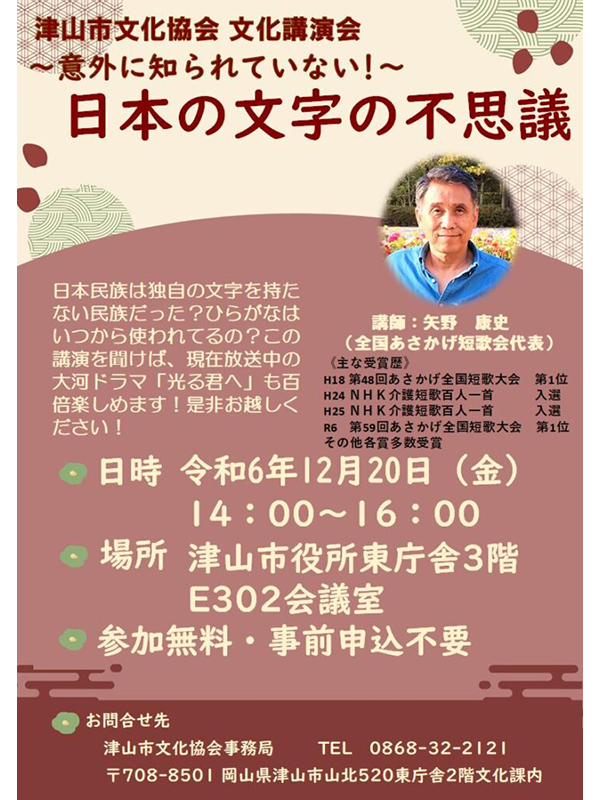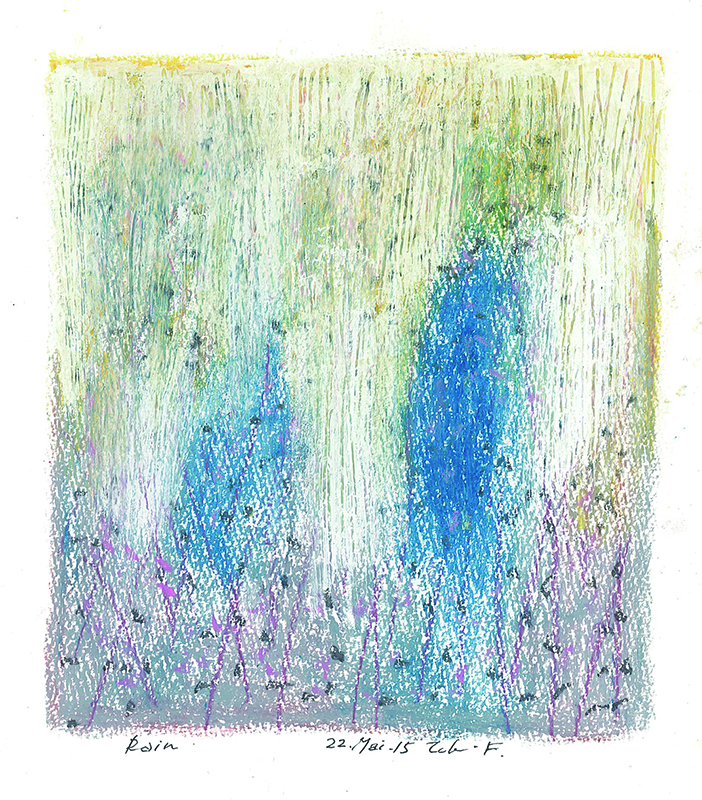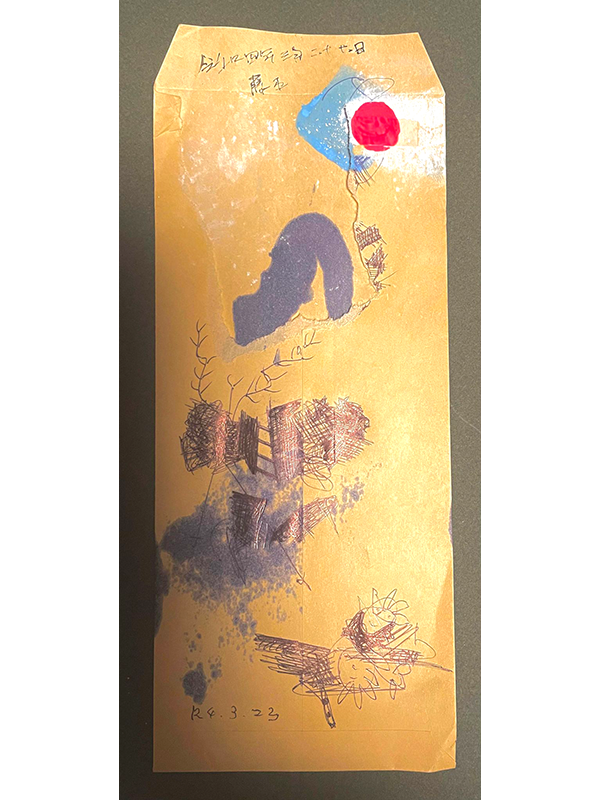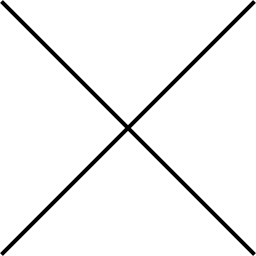前回は平安時代を中心に日本の家制度や氏、姓、苗字について書いてみました。
今回は鎌倉時代から室町時代について書いてみたいです。
鎌倉時代に入ると、武士が朝廷から離れた政権を樹立したこともあり、自分の土地を守る男性が土地から離れにくいため、嫁が夫の家に嫁ぐ『嫁迎え婚』が主流となってきます。しかし、この時代も、惣領制が確立され、女性が結婚しても夫とは異なる姓や財産を自らが持つ、夫に対しての独立性が高い関係でした。
惣領制とは、女性であっても男性と同じように土地など財産を相続し、女性の場合は自分が亡くなった後、男性であれば跡継ぎがなく家が絶えた時に、一族の長である総領家に対して財産を返却する制度です。
本格的な武士の時代に入ったことで、一族の繁栄のために結束を強める意味でも、この惣領制が広まって行ったと考えられています。
それが、世代が変わると徐々に、庶子家のなかにも二次的な惣領・庶子関係が形成されていきます。鎌倉時代も後半になる頃には、庶子家が独立を求めて、総領家との間に分断や対立が現れ始めました。
その後も庶子家の独立傾向が強まったことから、所領配分や惣領の統率権などを定めなおし、置文(おきぶみ)という文書により明文化されるようになります。
これは、事実上の惣領制再編となり、南北朝の時代に差し掛かる頃には、新たな惣領制が始まります。これにより、惣領家の庶子家統率権が強化されて、相続のうえでも一期分(いちごぶん/一代限りの相続)が一般化することになります。
しかしながら、鎌倉時代後期から室町時代にかけても、女性が一期分の対象となっており、男性と同じように一代限りの相続を行っています。
惣領制は厳格化されたものの、まだこの時代も男女間での相続に対する違いなどはない事が分かります。
これが、室町時代も後半に差し掛かると、大名間での争いごとが増えてきました。
そのため、武家では総領家の権限を強める必要ができてきました。そこで、庶子が相続からのぞかれ扶持(惣領の家来となっての俸給)をうけるようなり、一期分も衰退して嫡子単独相続制が成立し惣領制はなくなりました。
また、女性も一期分として与えられていた、私領や身の回りの物を、お化粧料等の名で持参させるように変化していきました。これが女性相続が出来なくなり始めたキッカケです。
さて、話は変わって名まえの方ですが、鎌倉時代に『嫁迎え婚』になっても、夫婦別姓は続いています。一期分で実家の財産を相続していることも影響しているのでしょうか。
実は、妻が実家の苗字を名乗るのは、戦国時代でも多くの家で続いています。しかし下剋上の世の中になり、苗字を持たなかった庶民から立身する者が現れます。この人達は、勝手に苗字を付けたり、仕える武将に付けてもらったりしました。その際に、女性も夫となる男性と同じ姓を名乗ります。
これが、日本における夫婦同姓の始まりです。しかし夫婦同姓は庶民から出世をしたもののみで、名家と呼ばれる家では、夫婦別姓が続いていました。
よく、インターネット等で検索してみると、『北条政子』や『日野富子』は、後世の人が便宜上そう呼んでいるだけで、本当は同姓だったなどと書いてありますが、北条政子は平政子として、公式に署名しています。また、日野富子も藤原富子との署名しかありません。
二人とも『源』としての署名は見つかっていないのです。
スペースの関係上、今回はここまでで、続きの江戸時代以降は次回に書きたいと思います。