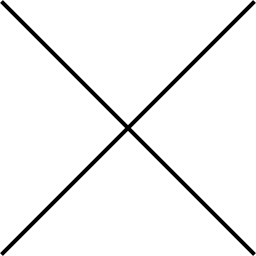掛詞を掘り下げる
今まで、何度か修辞法について書いてきました。
中でも、枕詞と掛詞と縁語は、和歌では多用されてきましたが、今の短歌では、ほとんど使われません。
それについては、明治に直接的で無用な装飾を排した、近代短歌が広まったことも理由ではありますが、それ以外にも大きな理由があると言われています。
それは、言葉の変化です。
具体的に説明したいので、以下の歌を見てください。
“はなの色は うつりにけりな いたづらに
わが身世にふる(降る、経る)
ながめ(長雨、眺め)せしまに”
有名な小野小町の歌です。文字にする際に仮名表記にして、言葉に複数の意味を持たせるように、詠んであります。
この中で、掛詞になっている『ふる』ですが、現代の発音では(降る)は(ふる)のままですが、(経る)は(ふる)から(へる)に変化しており、掛詞ではなくなっています。
続く(ながめ)についても(眺め)については(ながめ)のままですが、(長雨)については(ながあめ)というふうに変わっています。
このように、一首に2つも入っていた掛詞が現代語では0となってしまっているのです。
こちらも源宗于が詠んだ掛詞で有名な歌です。
“山ざとは ふゆぞさびしさ まさりける
人めも草も
かれ(離れ、枯れ)ぬとおもへば”
人目から離れ(かれ)と草も枯れといった、非常にきれいな掛詞です。
離れと枯れは、元々の語源は同じとされています。しかし、現代語で離れを(はなれ)でなく(かれ)と読む人がどの程度いるでしょうか。古語に興味を持っている人以外では、かなり見つけることが難しいでしょう。
こちらも、離れ(かれ)と読めない現代では、掛詞にはならなくなります。
さらに、もう一首。
“わが庵は 都のたつみ しかぞすむ
世をうぢ(宇治、憂し)山と
人はいふなり”
喜撰法師の歌です
この歌も非常に素晴らしく、うぢは「都のたつみ」から都の近くにある宇治山を示すかと思いきや、末句の「人はいふなり」で客観性を持たせることで、山奥→寂しい→憂し(うじ)を主として詠まれた歌だと感じさせます。
しかし、この歌の掛詞でも現代語では(憂し)という表現自体をされなくなっていますから、初めて見て、掛詞と気付く人は稀になっています。
このように、言葉の進化により新たな単語に読みが広がり、歌を詠む際に掛詞を使うことが、非常に難しくなっています。
今後、さらに言葉が多様化するにつれ、31音の中で掛詞を使うことの難易度が上がっていくでしょう。